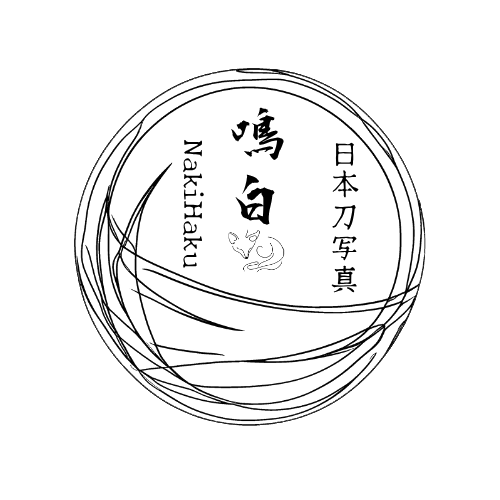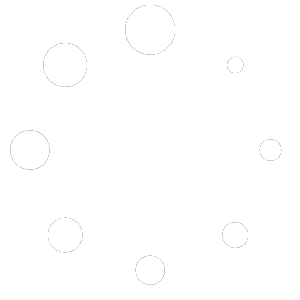今回よりストロボを使った撮影になります。
まずはストロボ1灯だけを使った基本的な撮影を学びます。ストロボ1灯でも撮影は問題なく行えます。
数があるに越したことはないですが、最初は1灯から学びましょう。
ストロボ1灯撮影の基本的な考え方
ストロボ1灯で撮影をする時に気をつけないといけないのが、光は1方向からしかない、ということです。
1方向かつ1灯だけのかなり限られた光しかありません。
ストロボのパワーにもよりますが、人間一人に綺麗に光を当てようと思ったら1灯ではかなり難しいです。
真正面から当てれば明るさは問題ないかもしれませんが、のっぺりとした感じのある光の仕上がりになります。

真正面からだとこのように光を無理やりバシッと当てました感があり、いい写真とは言い難いです。
一番簡単な配置といえばそうですが、ちゃんとした写真を撮影していきたいのであれば正面からはほぼ使わないでしょう。
ストロボ1灯の時は斜めにストロボを配置するのが多いです。
左斜めか右斜めか、これは被写体のポージングとか物理的に配置できるのかの問題もありますが左に配置することが多いです。
左側に1灯だけ置くとこのように左側は明るく、右側は光がないので暗くなります。

実際の人を相手にストロボをバンバン当てるのは気が引けるところですが、マネキンヘッドやフィギュアであれば問題なしです。
マネキンヘッドはネットでも買えますしダイソーでも買えます(100円ではないです)。
ライティングソフトで事前にイメージ図を作り、実際の撮影に活かします。
最初のうちは撮影時間のこともあってライティングを現地で考えている余裕もなければ、調整するのにも時間がかかります。
色々と考えすぎて撮影する時間がなくなってしまう事が一番の問題になるので、事前に決めておきましょう。
今度は右側に1灯だけ置いてみました。

考え方としては光がない方は影が濃くなる、です。
影が濃くなるのでキリッとした、威圧的な印象があります。男性を撮影する場合であればいいかもしれませんが、女性の場合は好まれない事が多いです。
なのでソフトボックス等を使って、ある程度光を柔らかくしつつ拡散させることで影も薄まります。
2灯使った場合と比べるとまだまだですが、1灯でも撮れないことはないです。
なので2灯以上ないと撮れない、ではなく1灯でも撮影はできる、と考えることが大事です。
パワーを上げても意味はない
ストロボ1灯のみで撮影する時に、反対側の明るさを確保しようと頑張って出力を上げていく人もいますが意味はないです。
暗い場所でパワーを上げて撮影するのは明るさを確保するという意味ではとても重要です。
どれだけ頑張っても光が当たっていないところは暗くなります。
むしろパワーを上げれば上げるほど、光のあたっている部分は明るくなって白飛びします。
なので意味がない、というよりも逆効果です。
白飛びしすぎた写真よりも影が濃く残っている写真のほうがまだ使えます。
むやみにパワーを上げるのではなく、その角度からは頑張っても無理であるということを覚えておきましょう。
屋外の場合であれば、光が足りない場合は光がある場所に移動したり他の明かりになるもので代用するしかありません。
ストロボ1灯のみ、他の明かりもないのであればある程度妥協する必要があります。
レフ板を活用する
ストロボ1灯ライティングの悩みどころの1つが、光があまりにも少ないという点です。
1灯しかないので光らせることが出来るのは1方向だけですし、どれだけパワーを上げても反対側が明るくなるわけではありません。
反対側を明るくしたいなら、反対側にも光が必要です。
そこで使うのがレフ板です。
太陽光を反射するためにレフ板を使う人も多いですが、ストロボでも考え方は同じです。
ストロボの反対側にレフ板を置いて、光を反射させてストロボほどではないですが影を飛ばすことが出来ます。
左側にストロボを配置して、レフ板を右側に置いて反射させてみます。
左:レフ板なし
右:レフ板あり

レフ板なしと比較してみましょう。
[twenty20 img1=”3209″ img2=”3211″ offset=”0.5″ before=”レフ板なし” after=”レフ板あり”]
1灯だけ使った場合と比べて反対側にも多少の光が入ってくるようになり影が消えました。
ストロボが1灯しかない状況だったとしてもレフ板等を使えば反対側にも光を補うことが出来るのです。
更にストロボと違って電池も電力も使わないので電池切れの心配もありません。
その反面、デメリットとしてはとにかく大きいです。
小さくても60cm、ちょっと大きめで80cm、もっと大きめで120cmと結構な大きさです。
もっと小さいのも売っていますが、小さければそれだけ光を当てる的が小さくなるので難易度も反射範囲も小さくなっていきます。
一番いいのは60cmくらいですが、ストロボと比べたら圧倒的なサイズです。
屋外であれば問題なく広げられますが、スタジオ撮影の場合は使えるとは限らないので注意しましょう。
どうしてもレフ板がない、使えない、という場合は白い何かで代用する方法もあります。
反射すればいいので、白くて大きいもの(冬だったら上着とか)で頑張って反射させる人もいます。
ただしレフ板と同レベルか、と言われたらそこまでは再現できないのでないよりマシ、程度で考えておきましょう。
クリップオンはほぼ使わない
クリップオンはカメラの上にストロボを付けて撮影する方法で、1灯しかない時に使っている人も多いです。
手軽にストロボを使える方法ではありますが、カメラの上にあるので重さが増すのと使い方がかなり限定されます。
安物のそれなりに大きなストロボを乗せると、たとえカメラとレンズが軽くても結構な重さになります。
重さが増えればそれだけ安定性も悪くなりますし、疲れやすくなります。
撮影に慣れていない時にカメラの重さで体力を奪われてしまうのはもったいないですし、ストロボを使う機会も減ってしまいます。
更にクリップオンの場合に出来る方法がカメラの上からのフラッシュか、天井に向けて光らせてバウンズさせる方法だけになります。
バウンズさせる方法については別途ご紹介します。
また、クリップオンの意外な使い方としてシャッター音が小さいカメラの時に「シャッターを押したことを伝えるフラッシュ」として使う人もいます。
被写体の人にシャッター音が聞こえない=いつシャッターを押しているのかわからないので、ストロボを光らせて伝えるそうです。
シャッターを押した時にストロボが光るのをうまく使った技です。
ストロボの光は全く使わず、ただ単にお知らせとしてだけ使っているので例外的な使い方ではありますが相手に伝えるという意味ではとてもいい方法です。
まとめ
最後にまとめです。
・ストロボ1灯の場合は光は1方向しかない
・ストロボがない側は光がないので暗くなる
・パワーを上げても反対側は明るくならない。レフ板とかを使って反射させる
・クリップオン(カメラの上にストロボ)は基本的に使わない