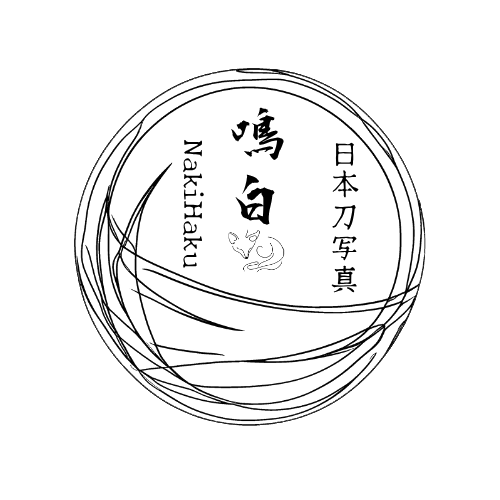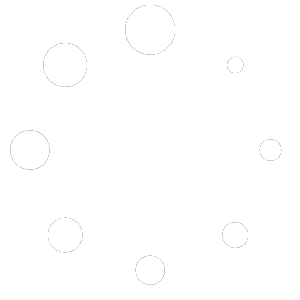今回はストロボと他の光を組み合わせた撮影、ミックス光での撮影方法です。
自然光は太陽の光で自然のものですが、それ以外にも普段使っている部屋の電気やLED照明といった光もあります。
部屋の電気では明るさが足りないことが多いので、ストロボを使わない場合はLED照明を別途用意します。
ストロボは一瞬だけ強い光を放つので、LED照明の光を飛ばしてストロボの一人勝ちになります。
自然光の場合は太陽の光がかなり強いので負けることはありませんが、逆にストロボが全く意味のない存在になります。
ストロボとそれ以外の光をうまく組み合わせることが出来れば、撮影の幅が広がります。
例えば色付きのライトとストロボを組み合わせると、こういった写真も撮れます。

これはストロボと定常光を組み合わせています。例えばスタジオやロケ地にある元からある良い感じの光があった時にその光も使いたい、という場合に活躍する技です。
逆にその光を消すことは出来ないが入れたくない、という時にも使えます。
鍵となるのはシャッタースピード
今回の撮影で鍵となるのはシャッタースピードです。
シャッタースピードが早ければ早いほど写真は暗くなり、動きが止まる写真が撮れます。
逆に遅くすればするほど明るくなりますが、動きのある被写体だとものすごいブレブレな写真になります。
普通に人を撮影する上ではシャッタースピードはある程度の早さが必要です。
ですが光をしっかり取り入れるとなるとシャッタースピードは遅くする必要があります。
ライトの強さにもよりますが、弱い光であればシャッタースピードを遅くしないと肉眼では見えていても写真には反映されません。
最初の画像の場合、シャッタースピードは1/40です。人が動いたらぶれる早さです。
これをシャッタースピードだけを1/2000にしてみます。

そうすると定常光の光は消えます。人物に向けて当てているストロボの光があるので、人物はしっかり見えるようになっています。
太陽光のようにものすごい強い光を放っていればシャッタースピードを早くしても問題ないですし、むしろ早くしないと白飛びします。
ストロボと組み合わせるとなれば、この場合はハイスピードシンクロが必須です。
ハイスピードシンクロは早いシャッタースピードでもストロボが付いてこれる機能です。ストロボの電池の減りが早くなるので注意が必要です。
Godox TT600はハイスピードシンクロ対応なので、早いシャッタースピードでも追いつきます。
太陽光とストロボの光を混ぜる場合はハイスピードシンクロにするのが一番簡単な方法です。
それ以外にもNDフィルターを使う方法もありますが、どちらもまた違った雰囲気になるのとNDフィルターを別途購入して取り付ける必要があります。
普通に撮影したいときには外さないといけないので手間はかかります。
シャッタースピードが早ければ早いほど太陽光の光は取り入れられず、暗くなりますがストロボが当たっている部分は明るいままです。
ストロボの光が当たる範囲はストロボのパワーに比例するので、シャッタースピードの変化による影響を殆ど受けません。
太陽光の当たっている部分は暗くなり、ストロボの光が当たる部分は明るくなります。
それ以外の場合も考え方としては同じですが、太陽光のような強い明かりではないのでシャッタースピードの調整が必要です。
屋内だったり屋外だったり頻繁に行き来するような撮影の場合、設定を頻繁に変えることになるのでしっかり抑えておきましょう。
太陽光と同じ設定で撮影すると、完全に背景が真っ暗になってストロボの光が当たった部分以外は見えなくなります。
黒背景じゃない場所で無理やり黒背景(のような)環境を作り出す際には有効ですが、光が微妙に届くと背景が見えるのであまりおすすめは出来ません。
光を混ぜるとどうなるか?
光を混ぜるとどうなるのか?についてですが、太陽光であれば昼の時間帯で夕方~夜を作り出す事が可能です。
LEDとかであればストロボと混ぜることで面白い写真を合成なしに撮ることが出来ます。
ストロボにカラーフィルターをつけただけでは出来ないような光を映し出すことが出来ます。
これを背景に使ってもいいですし、この写真のように被写体に直接当ててみてもいいですし、アイデア次第です。
ストロボ単体では生み出せないであろう光を作り出すためには必須です。
ただしストロボと真正面からぶつければ弱い光は完全に消えてしまうので、当たらないように注意しましょう。
また、光によっては色が混ざりあって違う色になってしまうこともあるので注意が必要です。
絵の具を混ぜたら色が変わるように、光の色も混ざれば変わります。
ただ絵の具と違うのは色によってはその色を打ち消すことが出来るので、カラーフィルターやホワイトバランスをうまく調整すれば一部の色を消すことも可能です。
例えば部屋全体が青色になっている場合には、そのまま撮影すれば被写体も全部青色になります。
人の肌が青色、というのは非常によろしくないので正常な色に戻したい時、青の場合はオレンジ系の色で打ち消すことが出来ます。
色相環を見ると色の関係性がわかるので、そのような環境だとわかっている場合は事前に調べておきましょう。
使っているストロボやカラーフィルターによっては色が予想外の方向にずれることもあるので、その点も考えておきましょう。
色無しでも混ぜることがある
今まで色が関係している話でしたが、色なしの普通の光でもストロボと他の光を併用するパターンもあります。
屋外ではなくスタジオ撮影になりますが、ストロボが物理的に置けない場所かつ床から光が出ている場合とかです。
専用のライトが床に仕込まれており、床からライトアップして背景を照らしていることがあります。
更に立ち入りできないようにフェンスとか柵が張られている場合はストロボも置けないので、この光を使うことになります。
その時にもミックスさせる必要があります。
床からのライトだけを使えば被写体は暗くなってシルエット上になってしまいます。
かといってストロボだけを使えば床のライトは完全に取り込まれず、被写体は明るいが背景は暗い状態になってしまいます。
背景もいれつつ被写体も綺麗に明るくしたい、ということになるとシャッタースピードをある程度遅くしないと両方の光を取り入れることが出来ません。
シャッタースピードが遅くなると手ブレしますし、被写体が動いてもブレるのでお互い動かないよう注意しましょう。
三脚を使うだけではなく、被写体にも動かないよう説明することが大事です。
ストロボのパワーが強すぎる時の対処法
ストロボによっては最弱パワーだったとしても、思っているより明るくなってしまっていたりすることがあります。
最弱なのでそれ以上弱く出来ないですし、物理的に距離を置けるなら距離を置けばいいだけですがそれ以上動かせないこともあります。
撮影スタジオの場合だと広さが決まってますし、狭い場所だとなおさらです。
ソフトボックスを使えばある程度パワーが落ちますが、結構幅を取りますし毎回使えるとは限りません。
そういったときは反対側や天井に向けます。
壁に当てたり天井に光を当ててバウンズさせる方法を利用してパワーを落とします。
なのでストロボのパワーを上げる必要はありますが、うまく調整すれば最弱よりも更に弱い光にすることが可能です。
もしくはカラーフィルターを使うと光量が落ちるのを利用して、色なしのフィルターとなるものを使って光量を落とす方法もあります。
即席で用意できるものでは難しいので事前に想定して準備しておく必要はありますが、カラーフィルターと同じビニール系の素材を使ったりします。
問題点としてはどの程度光量が落ちるのか予測が難しいので、事前の確認は必須です。
この場合、難点としては光が拡散されるので意図しないところも明るくなることがあります。
その場合は明るくしたくない部分に黒い壁を作って光が届かないようにすることで対応できます。壁があればいいので人間が壁になってもいいです。
アシスタントとか手の空いてる人がいれば壁になってもらいましょう。立ってもらうだけでOKです。
まとめ
最後にまとめです。
・ストロボの光はシャッタースピードにほぼ影響しない
・定常光はシャッタースピードで変わる
・太陽の光は非常に強いのでシャッタースピードを早くする必要がある