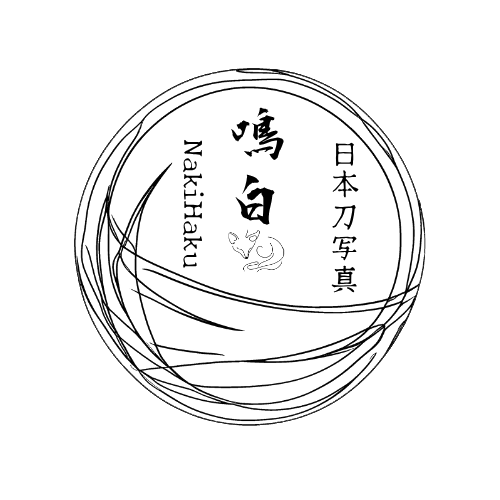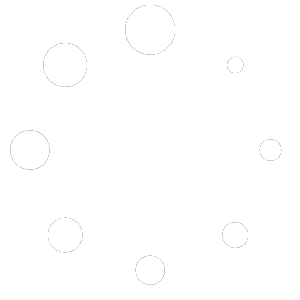ストロボを2灯以上使う事を多灯ライティングと呼び、ほとんどの撮影では2灯以上使われています。
2灯あることで撮影の幅が大きく広がりますし、ポートレート撮影とかでは2灯が基本です。
ですが1灯と同じ考え方では扱えないのが多灯ライティングです。
そして多くの人が挫折するのがストロボを複数台使った多灯ライティングです。
1灯ライティングとの大きな違い
多灯ライティングは1灯では光が届かなかった範囲までも照らすことが出来て、ライティング次第で可能性は無限にあります。
一般的には2灯を左右に置いて、影を飛ばして人物を明るく撮ります。
全体に光が行き届いて綺麗になりますし、影も完全に飛ばすことが出来るのでスタジオ撮影、屋外撮影どちらでも使えます。
1灯だけの場合は片方に光が入らず、影が強く出てきます。

ストロボを使った撮影の基本は2灯ライティングです。
1灯の場合はものすごく簡単で光は1方向だけでしたが、2灯になると2方向からの光になります。
今まで暗かった部分が明るくなる反面、明るさを調整しないと片方が白飛びする可能性も出てきます。
バランスを調整すればとても良い仕上がりになります。

その場の環境次第では左は暗いが右は明るい、といったこともあります。
その状態でストロボの設定をどちらも同じにしてしまうと、右側だけが明らかに明るくなりバランスが悪くなります。
多ければ多いほど撮影の幅は広がっていきますが、それと同時に段々と制御が難しくなります。
1方向だけの光を考えるのではなく、ストロボの数だけ考えることが増えるのが多灯ライティングです。
多灯ライティングでのストロボの配置と考え方
例えばストロボが3灯あれば左・右・後ろだったり、左・右・正面から足元だけ、といった使い方もできます。
実際、人物撮影でその人の身長が高い場合に足元が暗くなることがあります。
全身を照らしているつもりが、実際にはヒール等で身長が結構高くなっていて足元まで光が届かない時があります。
多灯ライティングでは、どこを明るくしたいのかを最初に決めます。
明るくしたい場所に向けてストロボを配置するので、明るくしたい場所が決まっていないと配置も決まりません。
人物撮影の場合は全身を撮るのか、バストアップ(上半身)だけを撮るのか、それによっても配置が変わります。
バストアップの撮影なのに全身を明るくしても意味ないですし、足元を明るくしても写りません。
被写体が女性でごく一般的な撮影をしたいのであれば、ストロボ2灯を左右に配置しますが陰影をはっきりつけたいならちょっとずらしたりします。
もしくは3灯用意して後ろからカラーフィルターを入れたストロボを使って、色を付けてみたりすることもあります。
今回は後ろ側に黄色を入れてみました。青い空がちょっと黄色がかった空になりました。

色を付けると先ほどと比べて一気に雰囲気を変えることが出来ます。
後ろからの1灯は色を付けるためのものですので、別になくても問題ありません。
無かったらないで寂しいところもあるので、綺麗に明るくしたいのであれば1灯入れておきたいところです。
もしくはこの後ろの1灯を明るさが足りない側に回してカバーする、という使い方もあります。
撮影の完成形のイメージを固める
どこにストロボを置くのかは非常に大切ですが、ストロボの配置を決める上で大事なことが完成形のイメージです。
ストロボを使うのはあくまで手段の1つです。
求めているイメージを完成させるためにストロボを使うのであって、正直なところストロボ以外でもなんでもいいです。
もしかしたら気付いていないだけで100均とかで売っている懐中電灯のほうが良かったりすることだってあります。
最終的にイメージしている写真が撮れれば使う機材は何でもいいのですが、大体はストロボで解決出来ます。
ただしこの完成形のイメージが出来上がっていないと、ストロボの配置も決まりません。
どの方向からどの程度のパワーで光を当てるべきか、何かしらのアクセサリーを使うべきか直当てでいくか、全てはイメージ次第です。
特に大事なのがアクセサリー類です。
ソフトボックスと言っても四角いのもあれば六角形だったり円形だったり、縦長のタイプだってあります。
形も大きさも全く違いますし当然ながら撮影に使えば結果も変わってきますので、何をどう使うのかを決める必要があります。
ちょっと近寄ったり離したりするだけでも結構変わりますので、イメージが出来ていないといつまでも納得のいく写真が撮れません。
最初に撮りたいイメージを確立させないことには、何か納得いかない写真だけになってしまいます。
特にストロボが複数ある環境の場合は、1つの間違いで全部がだめになることもあるのでとても大事です。
全部をフル活用する必要はない
ストロボが複数台あると全部をメインで使おうと思ってしまいがちですが、全てのストロボを完全に活かす必要はありません。
全部にソフトボックスを付ける必要はないですし、場合によってはかすめる程度の位置に置くことだってあります。
本当にちょっとかすめる程度なので存在感がものすごい薄いですし、それに1台使うのかと感じるかもしれませんがイメージしているものがそれで作れるならそれでいいのです。
被写体にしっかりと当てる役割のストロボもあれば、スポットライトみたいな感じの演出をするためだけにストロボを使うこともあります。
もしくはちょっとだけ足りない部分を補うために、もったいないと思うかもしれませんが必要に応じて使います。
全てのストロボが被写体又は背景をしっかり照らすために使われる、とは限らないと覚えておきましょう。
実際、足元だけ光が足りてなくて足元用に1灯使うことは多々あります。
注意点としては足りない部分を補いたい場合に、思っていたより広範囲が明るく照らされて一部が白飛びすることがあります。
その場合はストロボの角度を変えたり、位置を変えたりして微調整します。
位置が変われば明るさも変わってくるので、それもまた微調整が必要になります。
同じメーカーの違うストロボを使う方法もあり
複数のストロボ=全て同じ機種、と考える人もいますが実際には違う機種のストロボを使うこともあります。
例えばGodox TT600がコスプレ撮影では人気ですが、TT600ではどうしても明るさが足りないときが出てきます。
そんなときには同じくGodoxから出ている別の機種を組み合わせます。
例えばTT600を2台、AD200を1台、といった組み合わせにします。
どちらも同じメーカーの製品なので同じラジオスレーブで反応します。
TT600は小型軽量、パワーも結構ありますがAD200はそれを余裕で上回るパワーを持っています。
これらを組み合わせてAD200をメインライトとし、TT600で足りない部分をちょっとだけ補う、という使い方が出来ます。
これも多灯ライティングの1つです。
ただし機種が違うのでそれぞれの特性とパワーの違いをしっかり理解しておかないと白飛びするか真っ暗な写真が量産されます。
普通に撮影するだけでも機種の違うストロボを使うと難しいですが、同時に使うとなるとさらに難易度は上がります。
まず形状が全く違うので使えるソフトボックスも変わってきますし、専用のアクセサリーも用意されています。
TT600では使えるものでもAD200では使えない、というのは多々あります。
使う機材によって使えるアクセサリーも変わるので、最初のうちはストロボは同じメーカー・同じ機種で統一するのが安全です。
現状のままではどうしようもない、となったらもっとパワーのあるストロボに切り替えましょう。
光の重なりに注意する
多灯ライティングでは光の重なりに注意することも大切です。
ストロボが複数あり同時に光るので、配置によっては光が重なるところがあったりします。
光が重なればそれだけ明るくなるので重なった部分だけが白飛びしてしまったりすることがあります。
重なっている範囲が広ければ広いほど更に白飛びしていきます。
今回は右側からの光を強くなるようにしました。光が重なっているので左側と比べて右側がかなり明るくなっています。

白飛びさせないためには必要以上に光を当てないことです。
ストロボの位置・角度を変えて調整します。
よくあるのは必要だと思って光らせていたら実は不要だったパターンです。
調整しても明るい、と思ったら一旦そのストロボだけオフにして光がどうなるのかを見てみる、というのも1つです。
ストロボ1灯では心配する必要のないことですが、数が増えれば増えるほどこの光の重なりも多くなります。
特に壁がある場合、反射しないだろうと思っていても結構反射しているときがあります。
その影響で反対側の光が予想以上に強くなることもあるので、ストロボの光だけではなく周りにあるものにも目を向けてみましょう。
特に白いものは壁でもソフトボックスでも反射すると考えておきましょう。
その反射がいいこともあれば、よくないこともあります。特に何故か不必要な明るさが出てくる時には周りを見ることが大事です。
まとめ
最後にまとめです。
・多灯ライティングは全体に光を行き届けることが出来る
・多灯ライティングは手段であり必須ではない
・光が重なって白飛びしやすくなるので注意する
多灯ライティングは手段であって目的ではないので、光が足りていたり理想的な光が出来ているならストロボ1灯でいいです。
ストロボなしで撮影できるような環境であれば、そのまま撮影するのも1つです。
多灯ライティングを想定して撮影に挑むと機材が増えてしまい、撮影現場で持ってきたから使わなければ!と思ってしまうこともあります。
使わないで済むのなら使わないという選択肢もある、ということを忘れないようにしましょう。
持っていってなければ困るから持っていき、使う予定はないが持ってきた以上は使いたい、のは誰でも同じです。
そんなときは最終的にどんな写真を撮りたいか、のイメージを思い出しましょう。