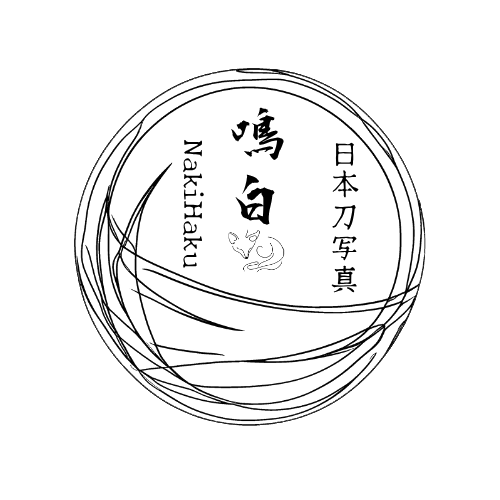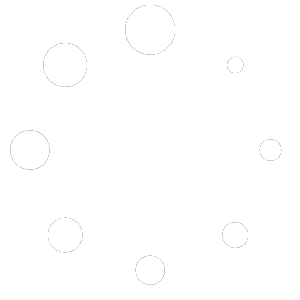ストロボをカメラから離して光らせることで撮影の幅が大きく広がります。
カメラの上からだけではなく、横だったり後ろだったり斜めだったりと様々な角度からストロボを光らせることが出来るようになります。
更に複数のストロボを同時に扱うことも可能になり、アイデア次第で様々な作品を生み出せるようになります。
今回はクリップオンではなく、カメラからストロボを離して扱う時(オフカメラ)に必要な機材をご紹介します。
カメラからストロボを離すために必要な機材
まずカメラからストロボを離したとき、そのままの状態ではもちろん光りません。
シャッターを押しても連動してくれず、光らせようと思ったらテストボタンを押しにいくしか方法がありません。
カメラとストロボを離した状態でシャッターを押した時に同時に光らせるためには、別の機材が必要です。
こちらの機材をカメラの上に取り付けます。
呼び方はラジオスレーブかコマンダーが一般的です。

これをカメラの上に付けて使用します。

ラジオスレーブの役割
ラジオスレーブの役割は主に2つあり
・遠隔でストロボを光らせる
・遠隔でストロボの設定を変える
です。
ストロボを光らせる、というのはシャッターを押した時にストロボを光らせるための命令を出す役割を持っています。
結構シンプルに見えますが、物によっては50mとか100m離れていても光るのでかなりすごいです。
といっても基本的には数m程度離して撮影するのが多いので、50mとかは不要ですが遠隔で光らせることが出来るのは便利です。
そしてもう1つがストロボの設定を変えることが出来る点です。
全ての項目を変えられるわけではないことが多いですが、変えることが多いのは光量(パワー)です。
最低限、パワー調整が出来るタイプのものであれば特に不便しません。
ただし安すぎるラジオスレーブの場合は残念ながらストロボを光らせることしか出来ない、というタイプもあります。
ラジオスレーブはストロボを遠隔操作するためのもの、と覚えておきましょう。
モニター付きとモニターなしが存在する
このラジオスレーブですが、モニター付きとモニターなしのタイプがあります。
モニターがないタイプには2種類あり、設定項目がほとんど存在しておらず本当にストロボを光らせるためだけにあるものと、専用アプリがありアプリ側で細かく設定できるタイプです。
前者は何も出来ない代わりに格安ですが、後者は結構高いです。
基本的にはモニター付きをおすすめします。
実際に想像してみるとわかりますが、カメラを持って撮影をする段階になってストロボのパワーを変えたい時は頻繁に出てきます。
その時にカメラの上のモニターを見ながら操作するか、スマホを取り出して操作するか、どっちの方が安全か?ということです。
三脚があるならどっちでもいいですが、常に三脚にカメラを載せて撮影している人はいません。
ほとんどの人が手持ちで撮影して、ストロボのパワーをラジオスレーブから変更する事が多いです。
それか直接ストロボのところまで行って操作する人もいますが、微調整であればできればその場で終えてしまいたいものです。
その時に片手にカメラ、片手にスマホで操作して設定していると安全面と手間を考えるとどうなのか?というのがあります。
モニターがない分、かなり小さく作られていますが仕事での撮影となるとスピード感も要求されてきます。
その時に毎回スマホ出して設定変えてスマホしまってカメラ構えて、というのは手間ですし見ている側としてもいいものではありません。
被写体=クライアントの場合には1つ1つの動作にも気を使ったほうがいい状況ですし、正直周りからは何をしているのかわかりません。
ストロボの設定を変えてるのか、何か違うことをしているのか、わかりませんが印象的にいいかどうかで言えば「良い」とは言い難い絵面になります。
ラジオスレーブがないと遠隔操作が出来ない
今後はもしかしたらカメラに搭載される可能性も否定出来ませんが、現状としてはストロボを遠隔操作するためにはラジオスレーブが必須です。
ラジオスレーブなしでカメラとストロボの電源を入れても、連動しないのでシャッターを押しても光りません。
初めてストロボを買った人がやってしまうことの1つにあるほど、ラジオスレーブは忘れられがちです。
ストロボ2灯持ってきたとしても、肝心の物がないということで1灯しか使えない事も多々あります。
ストロボとセットで販売されている事もありますが、大体は別売りされているので自分で探して注文しなければなりません。
セット売りだったとしても撮影現場に持ってこないと意味がないので、忘れないようにしましょう。
ストロボとラジオスレーブはセットで普段から持っていくようにする癖も大事です。
ラジオスレーブを使うメリット
ラジオスレーブを使う理由としては、カメラとストロボを離して使う他に複数台のストロボを同時に扱える点があります。
カメラの上なら1灯だけですが、外してしまえば2台でも3台でも扱うことが出来ます。
使える台数は機材次第ではありますが、大体は2~3灯あれば問題ありません。使える上限として10台を超えているのもあります。
実際の撮影で10台以上使うことはないですが、2~4台程度なら日常的に使う事があります。
屋内であればストロボがないと撮影が厳しいので、ストロボとラジオスレーブはセットで持っておきたいところです。
スタジオで用意されていることもありますが、それが自分の持っているカメラで使える保証はないので持っていくのが無難です。
特にオリンパス・パナソニックは他メーカーと比べて使える機材が限定されています。
ラジオスレーブを使う上での注意点
コスプレ撮影をする人にとっては日常的に起きている問題として、他の人のラジオスレーブにストロボが反応することが多々あります。
というのも、面白いことにコスプレ撮影をする人が使う機材は見事に偏っています。
皆が同じメーカーの同じ機種のストロボとラジオスレーブを持っているので、設定次第では反応します。
これはストロボのチャンネル設定が大きく関わっています。
本来はこういったことがないように1~20くらいあるチャンネルを自分で設定して、これは自分のストロボである、とラジオスレーブとペアリングさせます。
そうすることでペアリングされたラジオスレーブがついているカメラのシャッターが押されたとき、設定されたストロボも光ります。
ではこのチャンネルが被ってしまうとどうなるか?
厄介な事に複数のラジオスレーブとペアリングしてストロボが動作します。
もちろん、チャンネルが被っていてこっちのストロボが光るのであれば相手のストロボも光ります。
シャッターを押していないのにストロボが光った場合、まず近くに他のカメラマンがいないかを探しましょう。
誰もいないのに不定期にストロボが光るようであれば不具合が考えられますし、近くにいてその人がシャッターを押した瞬間に光るならチャンネルが被っていることになります。
もし被っていると気付いた場合はチャンネルを変更しましょう。
カメラマンが何人もいる場合はチャンネルを変えても他の人と被ることがあるので、被らないチャンネルを探してひたすら設定を変えます。
さすがに電波の届く範囲に20人近くいて全員同じ機材で同じチャンネルを使うことは考えられないのでいつかは避けられます。
お互いがほぼ同時に気付いた場合は話し合ってチャンネルを決めることもあります。
あまりにも被る場合はそういった話し合いをすることも必要になってきます。
他の人からしても「想定していない場所からの想定外のストロボの光」が入り込むことは問題なので、お互いにとって重要なことです。
シンクロケーブルを使う方法もあり
シンクロケーブルはカメラとストロボを接続するためのケーブルで、このケーブルを使っても離れた場所からストロボを光らせることが可能です。
ですが名前の通り、ケーブルが繋がってシンクロするのでケーブルが届く範囲に限定される上にケーブルがあるので足元注意です。
引っ掛けた時のことは考えたくないですが、有線ならではの確実性はあります。
あと差込口が一箇所しかないので、ストロボ1灯しか使えないデメリットもあります。
インターネットもそうですが有線と無線どっちが安定するかと言われたら、間違いなく有線です。
これは今も昔も変わらず言えることで、線をつないだ方が確実です。
ただそのケーブルがあったら足引っ掛けたりして危ないですし、物理的にケーブルが届かない場合も考えて無線のほうが便利ではあります。
それにカメラ側にも差込口は基本的に1つしかないので、扱えるストロボの台数も限定されます。
個人的には何よりケーブルに足引っ掛けてストロボかカメラが倒れることが一番怖いので、ラジオスレーブを使った無線派です。
被写体もカメラマンも誰も動かない、という条件付きであればケーブルを使うのも1つです。
ちなみにコスプレ撮影の場合、大型併せと呼ばれる20人以上参加する撮影の場合は無線じゃないとものすごく危険です。
全員同時に撮影、ではなく順番待ちになるので撮影待ちの人達があちこち移動するので引っ掛ける可能性が高いです。
1対1の撮影なら問題ないと思いますが、人数が増えてくる撮影であればケーブルは避けるのが無難です。
以上がストロボを遠隔操作出来るラジオスレーブです。
ストロボを遠隔操作できるかどうかで撮影の楽しさも大きく変わってきます。ストロボを購入する際には一緒に購入を検討してみましょう。