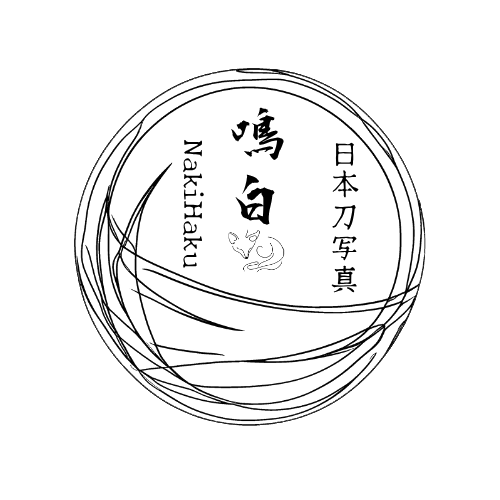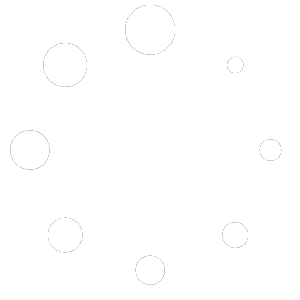第三章からはストロボを使った撮影になります。
ストロボはカメラのシャッターを押した時に一瞬だけ光るもので、普通の定常光を使ったときとはまた違った写真が出来ます。
副業としてもカメラマンとして活動するのであれば、ストロボを扱えないと仕事にならないくらいです。
ストロボとは?

ストロボの基本から確認していきましょう。
ストロボはシャッターを押した時だけ光る、一眼レフ・ミラーレス一眼の外部フラッシュです。
人気があるのはGodoxという中国メーカーのTT600という製品です。
価格が安い・丈夫・それなりに明るい・持ち運びにも苦労しない・単三電池で動く結構すごいストロボです。
コスプレ撮影をしているカメラマンなら大体がTT600を持っています。
相当特殊な環境で特殊な撮影をしない限りはTT600があれば仕事でも十分使えます。
ただし1灯だけだと撮影の幅が狭く、何かと明るさが足りないと感じる場面が多いので2灯あるのが望ましいです。
ストロボは一瞬だけ強い光を放つので、カメラの設定を間違えると白飛びではなく真っ白な写真を量産することにもなります。
特に明るい環境でストロボを使った撮影をする場合は注意が必要です。
明るいのにストロボを使うのか?と思われるかもしれませんが、後々その理由をご紹介します。
ストロボを使うときの注意点
カメラの設定
カメラの設定がかなり重要です。
ストロボの光は実際に使ってみるとわかりますが、結構強い明るさなのでカメラの設定は暗めで大丈夫です。
ISOは最低値、F値が高いレンズであってもストロボの光でカバーできます。
シャッタースピードはカメラやストロボ次第なところもありますが、大体が160~250あたりが最速値です。
ハイスピードシンクロというもっと早いシャッタースピードに対応しているものであれば、もっと早くても撮影できます。
TT600の場合はハイスピードシンクロ対応ですが、いきなり使うものではないので今はそういう機能があるんだ、程度で大丈夫です。
ちなみに今回のカメラの設定は以下になります。
ISO:100(最低値)
F値:8
SS:1/200
ちょっとF値が高いですが、ストロボのパワーを知っていただくためにちょっと暗めにしてみました。
ストロボの設定
今回はTT600を使って実際にストロボ側の設定を行います。
電源を入れるとこういった画面が出てきます。

機種が違えば画面構成も違ってきますので、今回は共通している部分だけご紹介します。
まずはストロボのパワー、明るさです。

1/32となっているのが明るさの強さです。
1/32が一番弱い光で1/1がフル発光、ものすごい強い光が出ますが電池の消費も激しいです。
またフル発光の場合は次に光るまでのタイムラグ(チャージ)が長いので、使う時は要注意です。
次に確認したいのがZoomの項目である20mmの部分です。
これは照射角を意味しており、照らす範囲を変えることが出来ます。

TT600の場合は20mm~200mmまで設定可能で、20mmであれば広い範囲を照らすことが出来ます。
逆に200mmにすると狭くなります。
今回はフル発光するほどではないので、1/32のパワーでZoomは20mmに設定しています。
明るさが足りないと思ったらストロボのパワーを上げるか、F値を下げましょう。
今回はこれで撮影します。
被写体とストロボの距離
最後に大事なのがストロボと被写体の距離です。
どんな光でもそうですが、被写体と近いか遠いかで明るさは変わってきます。
同じパワーだとしても近ければ明るいですし、遠ければ暗いです。
今回は被写体との距離は35cmです。
それぞれの位置関係は以下の図のようになっています。黄色い線がストロボの光のイメージです。
近すぎず遠すぎない距離から始めて、微調整します。
今回はいつもの撮影環境なので、この距離で進めます。
撮影した写真
実際に撮影した写真がこちらです。
カメラはLumix G9、レンズはLeica 45mm F2.8です。
これがストロボ1灯で撮った写真です。
先程の図のようにストロボが左側に1灯しかないので、右側に影が出来るようになります。
続けてストロボ2灯、右側にも入れてみます。
斜め前から2灯使った写真がこちらです。
左右の影が消えていい感じになりました。
実際に人物撮影をする時はその人に合わせて調整しましょう。
今回はストロボでこういう撮影が出来ます、程度の紹介ですが次回以降、ストロボの撮影に関するより詳しい解説です。
斜め前に置いてる理由も合わせて解説しますので、とりあえず今はストロボでこんな写真撮れるんだ、程度に思っていただければと思います。