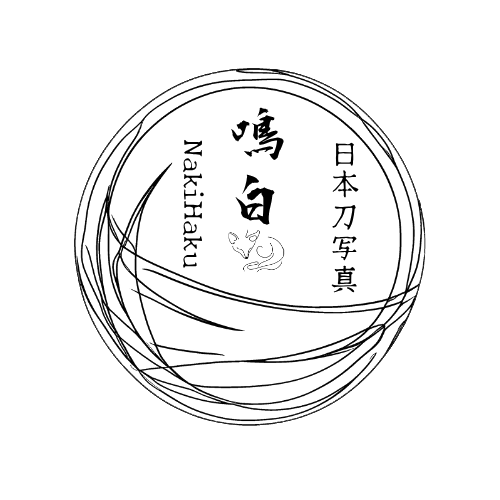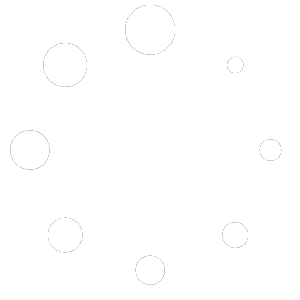カメラの基本設定の1つである、シャッタースピードについてです。
写真を撮るために最低限必要とされている設定は3つあるのは2-1でご紹介したとおりです。
今回はその1つであるシャッタースピードについて学びます。
最後に練習問題を用意していますので、実際に撮影してみましょう。
撮影したファイルを送信いただければ講師によるフィードバックも受けられます。
詳細は最後にまとめて記載していますのでそちらをご覧ください。
シャッタースピードとは?
2-1で軽く紹介しましたが、シャッタースピードは動きのある被写体の動きを止める事ができる設定です。
走っている人、自転車、スポーツ等の動きのある撮影ではシャッタースピードが重要です。
この設定を理解できていないと、被写体がぶれた何が写っているのかよくわからない写真ができあがります。
シャッタースピードはSSと表記されることもあり、○秒分の1(1/8000秒)で表されます。
1/1なら1秒ですし、1/2なら0.5秒です。
シャッターを押してから実際に写真として出てくるまでの時間です。
1/1000であれば0.001秒とシャッタースピードが早いです。
カメラによりますが、”3といった表示になっている時はシャッタースピードは遅いです。
上記の場合だと3秒なので、シャッターを押してから3秒後に撮影されることになります。
シャッタースピードの早い遅いはプロでもたまにどっちだったかを忘れることが多いほど、勘違いしやすい設定です。
現在のシャッタースピードが1/100だとします。
シャッタースピードを早くする、と言われたら1/200や1/400のように/の後ろの数字を大きくします。
シャッタースピードを遅くする、と言われたら1/50や1/10のように/の後ろの数字を小さくします。
こうやって文章で見ると当たり前に見えるかもしれませんが、実際に撮影の現場に入ったり人に説明するとなると話は別です。
F値もそうですが、言い間違えも多いところですので注意しましょう。
そしてF値同様、明るさにも影響します。
シャッタースピードが遅ければ明るくなり、早ければ暗くなります。
例:シャッタースピード 1/1000の写真(手持ち・三脚未使用)
1/1000で手持ちで動かない被写体であればぶれることはないです。走ってる新幹線の写真を撮るのに最低限必要と言われる早さです。
人物撮影であればぶれる心配はありません。
明るさはこの写真を基準とします。シャッタースピードを遅くしていくとよりぶれやすく明るくなります。
例2:シャッタースピード 1/10の写真(手持ち・三脚未使用)
※他の設定が同じままだと真っ白になったので多少調整しています。
人によってはギリギリ耐えられるかもしれないくらいのシャッタースピードです。手ブレ補正あり+練習すればぶれないようにも出来ます。
今回はなるべく動かないようにしていましたが、ちょっとぶれています。この程度のぶれならもう1回頑張れば抑えられると思います。
例3:シャッタースピード 1秒の写真(手持ち・三脚未使用)
1秒間完全に停止しなければならないとぶれる、という状況ですので手持ち撮影で頑張れば何とかなりますがかなりの体力を消耗します。
カメラを固定しない限りはぶれます。手ブレ補正がかなり強化されてきていますが、それでもまだまだ厳しいです。
ぶれている写真が欲しい、という依頼ならいいかもしれませんがこの写真を採用できるか、と言われたら普通は無理でしょう。
今回の被写体は動くことがないので、ぶれる原因としては撮影する側であるカメラを持っている人が動いているのが原因です。
シャッタースピードを遅くすればするほどもっとぶれていき、明るくなります。
シャッタースピードの目安
これらの数字はあくまで目安であり、実際の速さに合わせて微調整する必要があります。
走ってる新幹線を止めて撮影するためには、1/1000~1/8000が必要と言われています。
走っている人なら1/160程度で良いと言われています。
走るのが早い人の撮影であればもう少しシャッタースピードを早くするのがいいでしょう。
普通に歩いている人を撮影するのであれば、1/100は欲しいところです。
その人の速さ次第ですが、1/80あたりでブレることが多いです。
手ブレ補正のあるカメラでも、1/4あたりから少しずつブレてきます。
手ブレをさせないことだけに集中すれば1/4でもブレずに撮影できますが、かなりの集中力を使います。
それ以上遅くすると手ブレ補正ありでも辛くなります。
動かないものを撮る時はシャッタースピードは気にする必要はありません。
特に屋内かつ商品撮影とかをする場合はシャッタースピードは明るさ用の設定になります。
三脚を使えば手ブレを気にすることすら無いので更に良いです。
逆に遅くする場合ですが、遅くするパターンとしては明るさが欲しい場合とちょっと変わった撮影をしたい時に使います。
マジックアワーと呼ばれる、日の出の時間にシャッタースピードを数分に設定して撮影する方法です。
それ以外にもありますが、シャッタースピードを数秒~数分にするのは特殊な撮影のみです。
手ブレ補正があれば有利
手ブレ補正は全てのカメラに搭載されているわけではなく、それなりの価格帯のカメラのみにあります。
レンズ側にも搭載されている場合があります。
この手ブレ補正があると、多少シャッタースピードを遅くてもぶれない写真を撮ることが出来ます。
撮影環境が暗すぎて明るさを必要とする場合で、シャッタースピードで調整するしかない場合にとても有利です。
それ以外にも撮影現場があまりにも狭くて機材を使えない場合にも使えます。
明るさが足りない+狭くて機材も置けない撮影現場はよくあります。常に手持ちの機材全てを活用できるとは限りません。
たまにある、ではなく基本的に明るさが足りないものだと思っておいたほうがいいです。
明るさは自分で作り出すもの、と考えて準備することが大事です。
F値、シャッタースピード、ISO感度、それぞれの設定全てに明るさが影響しています。
更に被写体が動くのか動かないのか、どういった撮影をしたいのかを考えて設定値を決める必要があります。
遅くせざるを得ない場面でなくても、手ブレ補正は有利なのであって損はないです。
夜景撮影では三脚必須
夜景撮影をする時、シャッタースピードはかなり遅く設定します。
F値は絞ることになるのでそれだけで暗くなりますし、それ以前に肉眼で見ても既に真っ暗な状態です。
その状態で撮影をするとなると、明るさの確保が必須です。
明るさが足りなければ真っ暗な写真になりますし、機材でどうにか出来る話でもありません。
中には手持ちで撮影したい、という人もいるかもしれませんが手ブレ補正があっても夜景撮影はかなり厳しいです。
夜景撮影の場合、1/4とかではなく秒単位のシャッタースピードが必要です。
1/4より遅いシャッタースピードで手持ちで手ブレさせない、というのは結構難しいです。
呼吸する程度の動きでさえブレるので、息を止めてかつ完全に動かない状態になる必要があります。
息を止めるだけなら簡単ですが、全く動いてはならないというのは非常に難しいので三脚を使うのが一番楽で確実です。
また、三脚によってはシャッターを押すだけでも動いてしまいぶれてしまうので、遠隔操作したりレリーズと呼ばれる遠隔でシャッターを切れる機材を導入等が必要です。
いくつか三脚も試しましたが、安いものだとシャッターを押した瞬間にブレました。どれだけ頑張ってもシャッターを押すパワーに耐えられていませんでした。
夜景撮影を中心にしたい場合は、三脚はお金をかけてしっかりしたものを選ぶことが大事です。
練習課題
今回はシャッタースピードに特化した説明をしました。
通常は3つの基本設定すべてを組み合わせて撮影するのですが、まずは1つ1つ覚えることが大事です。
今回学んだことを実際に理解できているのか、確認用として以下の課題をご用意しました。
課題の取り組み、提出は任意ですが提出することで講師からのフィードバックを受けられます。
課題1.シャッタースピードを5秒で撮影してみよう(三脚なし、手持ち)
手持ちで5秒で撮影して、真っ白にならないようF値も調整してみましょう。
手持ちなのでブレブレの写真になりますが、今回は練習ですので気にせず撮影しましょう。
課題2.シャッタースピードを調整して、ギリギリブレない写真を撮影しよう(手持ち)
今度は手持ちでブレていない写真を撮影してみましょう。
シャッタースピードに正解はないので、自分にとってのベストな設定を探してみましょう。
手ブレ補正の有無は問いませんが、補正があるカメラ又はレンズであれば補正ありと補正なし、両方試してみましょう。
課題3.歩きながら写真を撮ってもぶれないようにしよう(手持ち)
シャッタースピードを適切に設定することができれば、歩きながら撮影してもぶれない写真を撮影できます。
動いているのは常に被写体とは限りません。自分自身が動いて撮影しないといけないことだってあります。
被写体が動きの読めない野生動物だと想定して、歩きながらでもぶれない写真を撮れるように練習してみましょう。
課題の提出について
課題の提出方法はメッセージ機能を使って担当フォトグラファーにファイルを添付して送信して下さい。
ファイル名とファイル形式はそれぞれ以下に変更して下さい。ファイル名が異なりますとどの講座のものか確認出来ず再提出となる場合がございます。
課題1のファイル名:2-3-1
課題2のファイル名:2-3-2
課題3のファイル名:2-3-3
ファイル形式:jpg